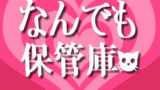YAHOO! JAPAN ニュースを見ていたら、クーリエ・ジャポン【2020年ベスト記事】「もう力尽きた…」中国・三峡ダムの“悲劇”と日本排除の“黒歴史” 危機を脱したのは本当?」という記事を見つけました。ダムについては素人ではないので、興味を持ったのですが、あまりにも中身がなく、週刊誌記事の寄せ集めの内容になっており、はっきり言って呆れてしまいました。
結局、このような専門知識が必要なテーマにもかかわらず、執筆者はなんの勉強もせずにネット情報を集めて書いたという典型的な見本のような記事になっています。
この記事の何がおかしいかを説明します。
意味不明の情報の羅列
書かれている文章を読むと、一般の読者にはもっともらしく感じるかも知れません。しかし、管理人から見たら、何も書かれていない! たったひとつのことさえ書かれていないイカサマ記事です。
まず、ダムが決壊するかどうかは、ダムのタイプにもよります。三峡ダムは重力式コンクリートダムなので、たとえ水がダム天端を越えても、ダム本体が決壊することはありません。
そもそも、そのようなことが起きないように、洪水吐という排水施設が設置されています。これは、確か200年に一度の洪水でも排水できるように設計されているはずです。
では、昨年の中国の洪水は、何年確率のものだったのでしょうか。記事には書かれていません。最も基本となる科学的な情報が示されていません。この情報を示さずに決壊する恐れ、など、何を言っているのか理解できない。それを主張するには、確率降雨量を調べる必要があります。そんな基本的なことも調べもせずに、素人の思い込みで決壊の危険性を煽るのは、報道機関として最低の行為です。
洪水吐からの排水にもかかわらずダム貯水位が上昇したとありますが、たぶん、下流の洪水位が高いことから、三峡ダムで排水量のコントロールをした結果なのでしょう。そんな当たり前のことは、管理事務所の記録で確認できます。ところが記事に一切書かれていません。机上の作文だからです。
最も腹立たしいのは、なんの根拠も示さず記事を書いておきながら、ダムと今回の洪水を結びつけて、理解不能な書き方で下流部の被害を強調するという手法。文章の構成が破綻しているので、ちょっと詳しい人が読めば、この執筆者の力量はすぐに分かるのですが、普通の読者には分からない。だから、【2020年ベスト記事】に選ばれる(笑)。
この記事って、机の上で、30分程度で書いた記事でしょう。なんの取材もせずに、専門家の知見も聞かずに、素人が思い込みだけで適当に仕上げた記事です。その証拠に、科学的データ、出典が一切ありません。
こんなものは、都市伝説を垂れ流しているだけの記事に過ぎません。
そもそも重力式コンクリートダムなので、ダムの重量で水を支えています。コンクリートの配合の話が少し記事の中にありますが、基本的に重ければよい、というのが重力式コンクリート式ダムです。ダムの本体内部は貧配合のセメントが使われます。手抜きではありません。セメントの発熱による熱クラックを防止するためセメントの量を減らすのです。
何を根拠に手抜きと言っているのでしょうか。
管理人は、中国のダムを見たことがありますが、とてもすばらしいものだと感じました。中身は知りませんが。でも、中国全土の大ダムが決壊せずに機能しているのですから、根拠のない都市伝説よりは、信頼性があります。
上で書いた基準は日本の場合であり、中国のダムの設計基準は知りません。記事にも一切書かれていない。
結局、クーリエ・ジャポンの記事は、素人の記者の作文であることが分かります。都市伝説を記事にしていると批判されても仕方のない、なんら科学的データも示していないフェイク記事です。
他のメディアの記事で、「鉄筋不足を懸念」と書かれていました。いつから、重力式コンクリートダムに鉄筋が使われるようになったのでしょうか。低配合セメントのコンクリートブロックを積み上げていくのが重力式コンクリートダムです。鉄筋? 何のことを言っているのでしょうか。その鉄筋って、どこに使われると考えて記事を書いているのでしょうか? 管理人には理解できません。もしかして、アーチダムと混同しているの?
三峡ダムで本当に注目すべき点は、堤体の変異が観測されているらしいこと。これはとても重要です。もし、これが本当だとするのであれば、ダムが転倒するリスクがあります。問題となるのは、地下浸透水です。この被圧地下水によりダム本体が持ち上げられ、堤体の安定性が失われ決壊につながります。これはとても恐ろしいリスクです。簡単にダムが決壊します。
次に着目すべき点は、堤体と岩盤との接触面からの漏水です。これが最も危険と言えます。接触面は、堤体の側面と底面にありますが、どの面からの漏水も要注意です。中国側の説明は、この点をしっかり説明しているのですが、メディアには何のことなのかちんぷんかんぷん。素人の思い込みで記事を書いているようです。
記事にするのであれば、素人の感想文・ねつ造記事ではなく、しっかりと専門家の意見を聞いて書くべきでしょう。
【2020年ベスト記事】ではなく、【2020年コロナ下で机上のみで書いてみたねつ造ベスト記事】という評価が正しいと思います。
ここまで読んだ上で、もう一度、クーリエ・ジャポンの記事を読んでみてください。ネット配信業者ってこのようなフェイクニュースを流すのか、と唖然とすると思います。
このような記事を書くのであれば、三峡ダムの設計基本諸元(洪水吐確率年など)、堤体変位データ、日本との設計諸元の違い、埋設計器データの変位、今回の洪水対処洪水吐ゲートオペレーション記録、など最も基本的な情報を提供すべきでしょう。クーリエ・ジャポンの記事は、このうち、たったひとつの情報・根拠も示さずに記事にしています。だからフェイク記事だと断定できます。
通常は、「専門家によれば」などと逃げ口を用意した書き方をするようですが、この記事に関してはそのような記述はありません。文責はすべて執筆者が負うという覚悟なのでしょう。そして、クーリエ・ジャポン【2020年ベスト記事】に選ばれた?
会社ぐるみでフェイク記事を堂々と発信する気満々、という印象を受けます。
三峡ダム決壊の煽り記事の発端は、Google Earthに表示された三峡ダムの形状が歪んでいたことにありました。これは、単なるGoogle Earthの技術上のゆがみの問題で、のちに、Googleはこれを修正しています。
ということで、煽りメディアは、その根拠を失ったことになります。煽ったメディアの黒歴史がまた1つ増えたということでしょう。なんとも低レベルな都市伝説です。
ダム諸元
ダムサイト 中国湖北省宜昌市三斗坪
建設工期 1993年~2009年
堤高 181m
堤長 2,309.47m
有効貯水容量 393億㎥
洪水調節容量 222億㎥
設計洪水量 124,300㎥/s
湛水面積 1,084Km2